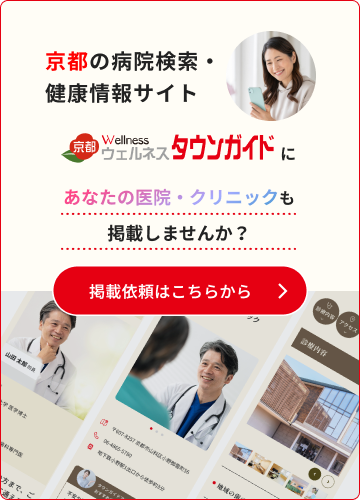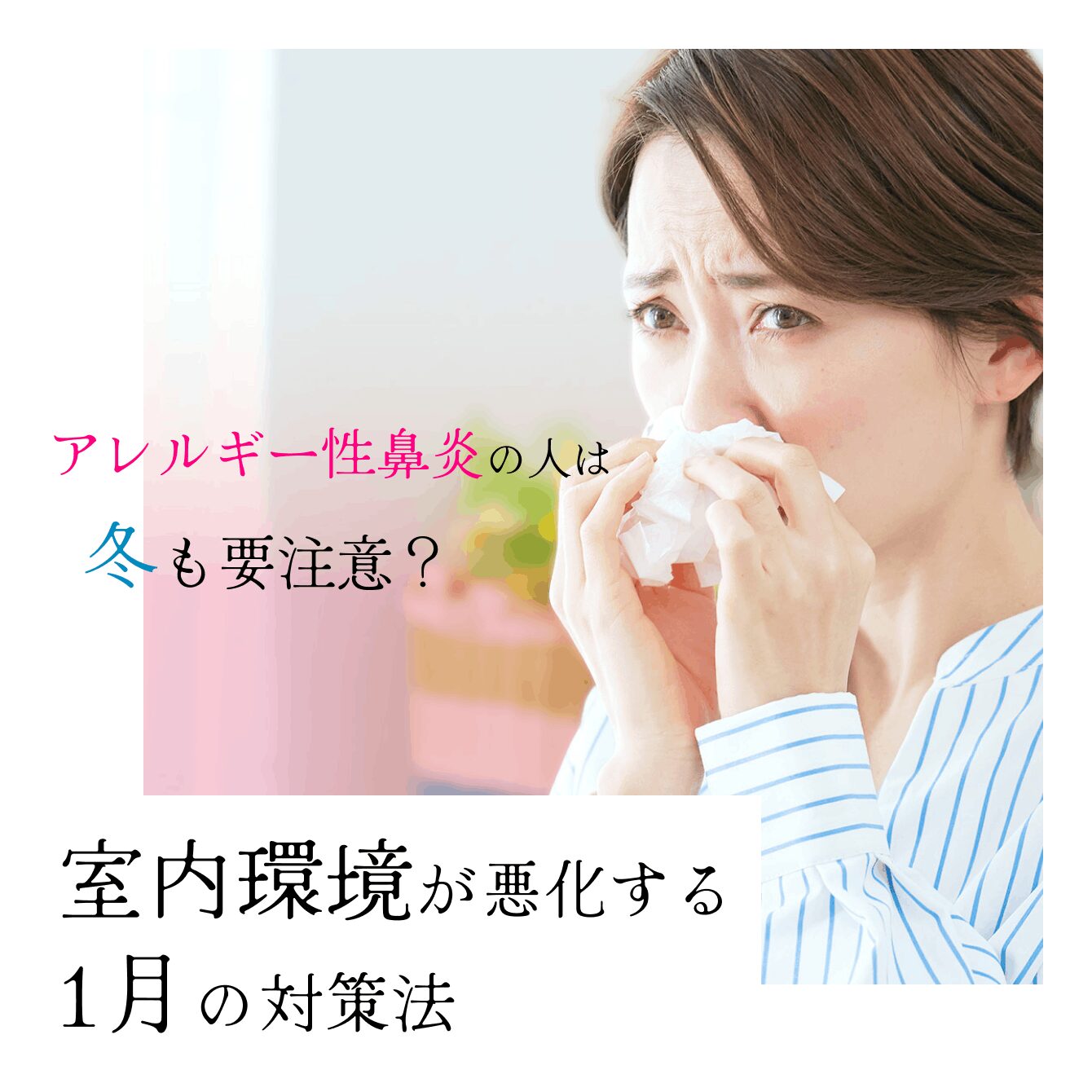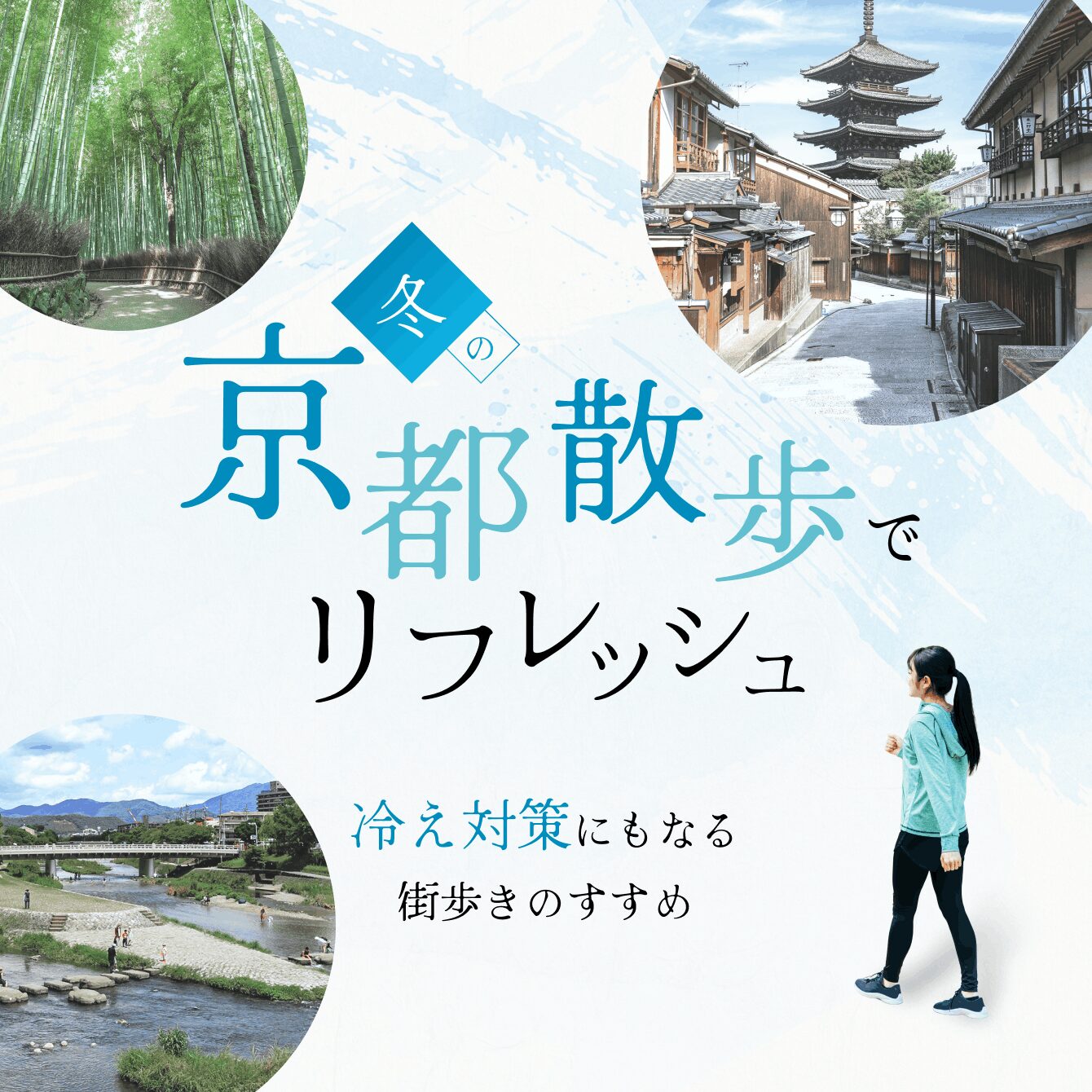秋の眠れない夜は“光と温度”のリズムがカギ|快眠環境の整え方

秋になると「眠れない」が増える理由
「涼しくなったのに、なぜか眠れない」「夜中に何度も目が覚めてしまう」
そんな声が増えるのが、秋です。
秋は一見、過ごしやすい季節に思えますが、実は“眠りのリズム”が乱れやすい季節。
その理由は、光と温度の変化にあります。
夏の間は日照時間が長く、体は自然と活動的になります。
しかし秋になると、日が短くなり、朝夕の気温差が大きくなるため、
体内時計を司る自律神経が乱れやすくなるのです。
体が「昼なのか夜なのか」を正しく認識できなくなると、
眠気を誘うホルモン「メラトニン」の分泌リズムが崩れ、
眠りの質が低下してしまいます。
では、どうすればこの季節を心地よく眠れるようにできるのでしょうか。
ポイントは、“光”と“温度”のリズムを整えることにあります。
1. 光のリズムを整える|朝と夜の光で体内時計をリセット

朝の光を「浴びる」ことで、睡眠ホルモンをリセット
人の体は、朝日を浴びることで体内時計をリセットします。
目から光が入ると、脳の「視交叉上核」という部分が反応し、
「メラトニン」の分泌をストップさせ、「セロトニン(覚醒ホルモン)」を活性化します。
秋は日の出が遅くなるため、起床時間と日の光が合わなくなりがち。
それが「朝起きてもぼんやり」「夜になっても眠くならない」原因になります。
ポイント
- 起きたらまずカーテンを開けて自然光を浴びる
- 雨の日や曇りの日は、照明をしっかり明るくする
- 朝の散歩やストレッチで体を動かす
朝に光を取り入れることで、約14〜16時間後に再びメラトニンが分泌され、
自然な眠気が訪れるようになります。
夜の光を「減らす」ことで、眠りを誘う
一方で、夜に明るい光を浴びすぎると、体は「まだ昼だ」と勘違いします。
特に、スマートフォンやPCのブルーライトは、
メラトニン分泌を強く抑制してしまうため注意が必要です。
ポイント
- 就寝の1時間前にはスマホ・パソコンをオフに
- 照明は暖色系(オレンジ系)のやわらかい光に
- 寝室の照度は抑える
夜は“光を減らす時間”と意識して、
視覚的にもリラックスできる空間づくりを心がけましょう。
2. 温度のリズムを整える|眠りに最適な「温度と湿度」

快眠に理想的な寝室環境は「温度20℃前後・湿度50〜60%」
眠りに入るとき、体温は自然に下がることで脳と体を休ませます。
しかし、室温が高すぎたり低すぎたりすると、この“体温リズム”が妨げられてしまいます。
秋は昼夜の寒暖差が激しく、寝具の調整が難しい季節。
特に、夏のままの寝具を使っていると、夜中に体が冷えて目が覚める原因になります。
理想の環境づくり
- 室温:19〜22℃前後
- 湿度:50〜60%
- 掛け布団は軽く保温性の高い素材を
- 足元が冷える場合は、湯たんぽやレッグウォーマーを使用
エアコンや加湿器をうまく使って、「暑すぎず、寒すぎず」をキープしましょう。
入浴で“体温リズム”を味方に
寝る前の入浴も、体温のコントロールに役立ちます。
38〜40℃のぬるめのお湯に15〜20分ほど浸かると、
いったん上がった体温が下がるタイミングで自然な眠気が訪れます。
入浴の理想タイミングは「就寝の1〜2時間前」。
その後の体温低下がスムーズに起こり、深い眠りに入りやすくなります。
Q&A:秋の不眠によくある質問
Q1. 寝る直前のスマホが眠りに影響するって本当?
A. はい。本当です。ブルーライトはメラトニンの分泌を抑えるため、
寝つきが悪くなります。就寝1時間前にはスマホを見ないのが理想です。
Q2. 寒くて眠れないとき、暖房をつけたまま寝ても大丈夫?
A. 低温(20℃前後)であればOKですが、乾燥を防ぐために加湿器を併用しましょう。
寝る前に暖房を入れておき、寝入りに切るタイマー設定もおすすめです。
Q3. 寝酒をすると眠りやすい気がしますが、問題ありませんか?
A. 一時的に寝つきはよくなりますが、アルコールは睡眠の質を下げ、
夜中の覚醒を増やします。就寝3時間前以降の飲酒は控えましょう。
まとめ:秋の夜長は「光と温度」で眠りをデザインする

秋は、日照時間の短縮と気温差によって体内リズムが乱れやすく、
眠りの質が低下しやすい季節です。
しかし、
- 朝に光を浴びて体内時計をリセット
- 夜は照明を落として脳を休ませる
- 室温・湿度を整えて心地よい寝室をつくる
といった工夫で、自然な眠りは取り戻せます。
眠りは“1日の終わり”ではなく、“明日を整える準備時間”。
光と温度のリズムを味方につけて、秋の夜を穏やかに過ごしましょう。
参考文献
- 厚生労働省「健康づくりのための睡眠指針2014」